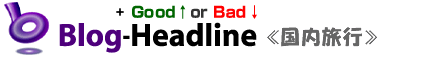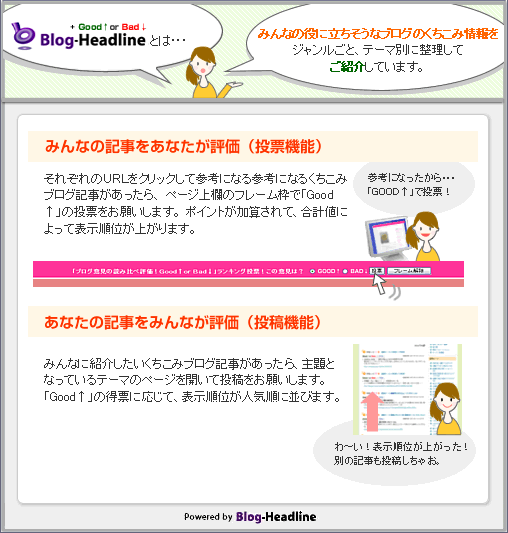「道後温泉」に関するブロガーの意見で、みんなの参考になりそうなブログ記事を集めています。自薦による投稿も受け付けているので、オリジナルな意見のブログ記事があったら、どしどし投稿してください。
土曜日と言う事もあって、観光客だらけで、3階個室は満室状態だったんですが、タイミングよく空室が出て、3階個室券ゲット!!
世に聞く名湯、道後温泉の高級旅館「ふなや」に宿泊する機会にめぐまれた。
朝は六時から下の写真の赤いステンドグラスの櫓にある太鼓の音とともにオープンで行列ができます。、霊の湯の一番湯に入ってきました。すっごく贅沢な気分でした。
道後温泉での〜んびりしてまふ。ここ道後温泉は日本最古の温泉として有名です。でも、私としては夏目漱石の坊ちゃんで記憶にあるかな^^;
日帰り入浴ができる温泉を調べて、行き先は道後温泉大和屋本店になりました。ここでまずは腹ごしらえです。
源泉掛け流しのお湯は42度ぐらいというコトでしたが、意外と平気な自分にビックリ。(笑)3000年の歴史のある温泉の質感は「効きそう!」と感じる質感でした☆
温泉の泉質は「単純温泉」で、非常に穏やかでやさしいお湯でした。特に驚いたのが、お湯につかるとすぐに体がぽかぽかしてきて体の芯から温まることです
正直、もっと汚いところかと想像していたら(汗)、ピカピカに磨かれた木の床が印象的で、脱衣所も浴場も、古いながらも清潔な感じでした。
珍しく、純和風な作りの旅館でした。とにかく雰囲気と接客がよかったです。一言で言うと「お客を放っているようで放っていない、さりげない接客」でしょうか。
神々の湯殿での初風呂は、心地よく、スローに、ゆらゆらと湯煙にただよう気分。日本最古の道後温泉は、大国主命と少彦名の命が親しんだともいわれています。
お湯は、奥道後の源泉らしく、肌ざわりの良いツルツルしたお湯である。浴槽の縁(ふち)に木の枕があり寝湯を楽しめるようになっている。
これに乗って松山駅から道後温泉へここは千と千尋の神隠しのモデルになった建物とも言われている、たしかに古そうだが重厚な感じもする。
肝心の泉質ですが、さらさらとして特徴ないのかなぁ〜と思いきや、短い時間でぽかぽかに温まります。更に入浴後も気持ちが良くて、いいお湯だなぁと思いました。
泉質はアルカリ性単純温泉で、ぬめりはほとんどなく、さっぱりとさわやかな入浴感だ。風呂上りには肌がすべすべになり、いつまでも暖かさが持続して気持ちよかった。
千と千尋のモデルとなったと言われ、坊ちゃんにも出てきた、国の重要文化財でもある観光名所。日本で唯一皇族専用の風呂があるってことを今回はじめて知った。
市内にある道後温泉で、お風呂に入りました。歴史の古い道後温泉のお湯は、日本でも有数の、名湯です。
千と千尋の舞台になった温泉施設です。石造りの浴槽につかりながら、映像がくるくる回転しました。
湯船に入ると、肌がスベスベした。ゆっくり温まり、風呂上りの一杯をと泊まっているホテルの1階のレストランに入る。「鯛のくいしんぼ」という寿司があるのでそれを頼む。
たくさんの下駄箱に囲まれた受付をすり抜けると、1階左側が男性風呂だ。教室1つ分くらいの浴室の中央に石の桶がある。そこから、お湯が注ぎ込まれている。
神の湯にも入ったがこちらはそれなりの人数がいた。神の湯のほうが浴槽は断然大きい。湯は無色透明無臭。わずかにぬめり感はあるがさっぱりとした湯だ。
道後温泉本館は歴史を感じる造りで浴場内も古い銭湯みたいな感じかな。泉質は美人の湯のアルカリ性単純泉!やわらかい感じのお湯でしたよ☆
手。そう、手湯なんです!初めて見たけど、改めて手湯と書かなくてもいいんじゃない、などと思いながらも、結構湯量が豊富で、思わず手を洗ってしまいましたが・・・
ぶっちゃけ泉質はわからなかったがとりあえずスピリチュアルな感じがあったのでこのポイント。風呂もとりあえずスピリチュアルな感じでした。
霊の湯温泉に入ると、皇族専用浴室として作られた、「又新殿 (ゆうしんでん)」が見学料250円のところ無料で見られる。夏目漱石ゆかりの「坊ちゃんの間」は常時無料。
素晴らしい!!! 建物の造り、石造りの浴室、滑らかな石造りの湯舟、湯舟の縁からオーバーフローで掛け流されるクリアな単純泉…
道後温泉は 聖徳太子も来湯されたという 古〜い歴史ある温泉道後温泉本館には 広々とした「神の湯」と少し小さめの「霊の湯」があり、5つの浴室があります
せっかくなので大正ロマンを感じる道後温泉本館に突入する。ゆっくりするぞ〜と、身体を洗って湯船に入るもメチャメチャ熱い〜!
透明ではあるが、泉質は、アルカリ性単純泉で、日本人の肌に合うなめらかなお湯で、明治以来の伝統として暖かい落ち着いた感じを保持していた。
風呂は上・中・下と階級?がありまして。。。上流階級バージョンだと浴衣やお茶やお団子が個室で楽しめるようになってました。下流階級の私はもちろん、下の下で"^_^"
| << 前のテーマへ | | メイン | | 次のテーマへ >> |